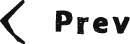南高梅で始める梅仕事!梅干し・梅シロップの漬け方・作り方
今年も梅の季節がやってきましたね!スーパーや道の駅に並んだ、みずみずしい梅を見ると「今年は何か梅仕事に挑戦してみようかな?」と思う方も多いのではないでしょうか。
でも初めて挑戦する方は「自分で梅干しや梅シロップを作るってなんだか難しそう…」と感じるかもしれませんね。
そんな方のために今回は、初めての方でも失敗しない南高梅を使った梅干しと梅シロップの漬け方・作り方をご紹介します。ぜひこの機会に梅仕事を楽しんでみましょう。
目次
リンクをクリックするとその項目までジャンプします。1.南高梅とは?

「梅」と一口に言っても、たくさんの品種があります。その中でも、梅仕事をするのに人気な梅が「南高梅(なんこうばい)」です。
南高梅は、和歌山県を代表する梅の品種です。和歌山県産の梅は、全国の梅の収穫高の6割を占めています。南高梅は、和歌山のブランド梅であり、梅のトップブランドでもあるのです。
特徴
南高梅には以下のような特徴があります。
・非常に厚い果肉
・薄くてやわらかな皮
・小さな種
・豊かで甘い香り
この果肉の厚さと皮の薄さ、豊かな香りが、梅干しや梅シロップの風味を格段に引き上げてくれるんです。まさに南高梅は、梅仕事にぴったりの理想的な梅なのです。
旬の時期
南高梅の旬の時期は、主に5月下旬から6月下旬頃です。梅の用途によって、青い状態の「青梅」の時期、黄色く熟した「完熟梅」の時期と旬がことなります。
青梅は、未熟なうちに収穫する収穫初期の青い状態の梅です。主に梅シロップや梅酒に向いています。
完熟梅は、熟してから収穫する収穫後期の黄色く色づき、甘い香りが漂う状態の梅。梅干しに最も適しています。
南高梅と普通の梅の違い
南高梅は和歌山県紀州地方の特産で、大粒で果肉が厚く、皮が薄い特徴があります。熟すと芳醇な甘い香りが漂い、甘みと酸味のバランスが絶妙なのです。そのため、高級梅干しや梅酒、梅シロップに使われることが多く贈答品としても高い人気があります。
一方、「普通の梅」は日本各地で栽培され、南高梅に比べて実が小さく、酸味が強い傾向があります。価格も手ごろで、梅シロップや梅ジャム、料理の風味付けなど、日常使いに幅広く使用されています。
このように、南高梅は他の品種と比べても、特に梅干しや梅シロップを作る上で美味しさが抜群なんです!せっかく手作りするなら、最高の梅「南高梅」がおすすめです。
2.梅仕事の前に基本の道具と準備
梅仕事の前に、いくつか準備しておくことがあります。準備をしっかり行うことが、カビを防ぎ、美味しい梅干し、梅シロップを作るための重要なポイントになります。
梅仕事に必要な基本的な道具
まずは、必要な道具を揃えましょう。作りたいものに合わせた保存容器を用意することが大切です。
【梅干し作りに必要な道具】
・保存容器:ホーローや陶器、口が大きなガラス瓶(1kgの梅の場合、2L以上の容器)
・重石(ペットボトルやビニール袋に水を入れたものでも代用可能)
・落し蓋
【梅シロップ作りに必要な道具】
・保存容器:密封できるガラス瓶(1kgの梅の場合、3L以上の容器)
【梅仕事共通の道具】
・竹串(爪楊枝)
・清潔な布巾やキッチンペーパー
・ザルまたはバット
・計量器、計量カップ
・ボウル
・菜箸
カビ予防のための消毒方法
梅仕事で最も気をつけたいのが「カビ」です。容器や道具に少しでも雑菌が残っていると、せっかくの梅が台無しになってしまうことも。徹底した消毒で、カビを未然に防ぎましょう!
消毒方法は煮沸消毒とアルコール消毒の2種類があります。それそれの消毒方法を紹介します。
【煮沸消毒】
1.大きな鍋に、保存容器が完全に浸かるくらいの水を入れます。
2.保存容器を鍋に入れ、火にかけて沸騰させます。(※急な温度変化でガラスが割れるのを防ぐため、保存容器を沸騰したお湯にいきなり入れるのは避けてください。)
3.沸騰後、5~10分程度煮沸します。
4.火を止め、保存容器を清潔な布巾の上に置き、完全に自然乾燥させます。
【アルコール消毒】
煮沸できない容器や、より手軽に消毒したい場合に便利です。
1.消毒用エタノール(食品にも使えるもの)か度数が35度以上のお酒(ホワイトリカーなど)を清潔なキッチンペーパーに含ませ、容器の内側やフタ、道具などを丁寧に隅々まで拭きます。
2.アルコールが揮発するまで、十分に乾燥させます。
重石や落し蓋などの道具の消毒も忘れすに行ってくださいね。
3.梅干しの漬け方・作り方

材料の分量については、梅1kgを基準として紹介します。この比率を参考に、漬ける梅の量に合わせて調整してくださいね。
材料
・南高梅:1kg(完熟梅がおすすめ)
・粗塩:200g(梅の重量の20%)
漬け方・作り方の手順
①梅の下準備
1.傷んでいる梅を取り除く。
2.梅をボウルに入れ丁寧に水洗いする。(青梅を使っている場合、水に1時間ほどつけてアク抜きをします。)
3.洗った梅はザルなどにあげ、1粒ずつ布巾やキッチンペーパーで完全に水気を切る。
4.竹串でヘタを取り除く。
②塩漬け
1.消毒済みの保存容器の底に、粗塩を少量敷きます。
2.梅を一段並べ、その上から粗塩を均等に振りかけます。
3.この作業を繰り返し、梅と塩を交互に重ねていきます。一番上は塩で蓋をするように覆うようにします。
4.落し蓋をして、梅の重量2倍の重石を乗せます。
5.必ず蓋で容器を密閉して冷暗所で数日置きます。(蓋が無い場合はビニールや食品用ラップを被せてください。)
③梅酢が上がるまで待つ
1.梅酢(梅からの水分)が出てくるまで、数日~1週間ほど待ちます。(毎日様子を確認します。)
2.梅全体が梅酢に浸かった状態になったら、梅が潰れるのを防ぐために重石を梅の重量の1/2〜2/3くらいまで減らして軽くします。(もし梅酢がなかなか上がらない場合は、重石を少し重くしてみましょう。)
3.梅酢に漬かった状態で1ヶ月、塩が溶け切るまで冷暗所に保管します。
④土用干し
1.梅雨明けの7月中旬ごろからの天気が安定した3日間を狙って梅を乾燥させます。
2.大きなザルや竹籠に梅を重ならないように並べ、日中は日当たりの良い場所で干します。
3.夕方には屋内(屋根の下)に取り込みます。
4.2日目に梅をひっくり返して全体が均一に乾くようにします。
5.3日3晩を目安に日中は天日干し、夜は屋内に干すことを繰り返します。
6.梅の表面が乾き、指で押すと適度な弾力があり、シワが寄っていれば完成です。
梅干しを作るときのポイント
梅干し作りは季節を考えて取り組むことが大切です。土用干しは梅雨明け、7月中旬からの晴天が続くときに行うため、塩漬けを6月中旬から下旬頃には行えると最適です。土用干しは途中で雨が降るとカビの原因になるので、天気予報をしっかり確認しましょう。
保存方法と賞味期限
梅干しは直射日光が当たらず、高温多湿ではない、冷暗所で保存しましょう。容器は密閉できるものが理想です。
きちんと漬けられて保存状態が良ければ1年程度、場合によっては1年以上保存が可能です。ただし、減塩梅干しの場合は、冷蔵庫で保存し早めに食べきるようにしましょう。
4.梅シロップの漬け方・作り方

材料の分量については、梅干しの作り方同様梅1kgを基準として紹介します。この比率を参考に、漬ける梅の量に合わせて調整してください。
材料
・南高梅:1kg(青梅または完熟梅)
・氷砂糖: 1kg(梅の重量と同量)
漬け方・作り方の手順
①梅の下準備
1.傷んでいる梅を取り除く。
2.梅をボウルに入れ丁寧に水洗いする。(青梅を使っている場合、水に1時間ほどつけてアク抜きをします。)
3.洗った梅はザルなどにあげ、1粒ずつ布巾やキッチンペーパーで完全に水気を切る。
4.竹串でヘタを取り除く。
②保存容器に詰める
1.消毒済みの保存容器の底に、氷砂糖を少量敷きます。
2.梅を一段並べ、その上から氷砂糖を均等に振りかけます。
3.この作業を繰り返し、梅と氷砂糖を交互に重ね一番上は氷砂糖で蓋をするように覆います。
③冷暗所で熟成させる
1.容器は直射日光の当たらない、涼しい冷暗所に置きます。
2.毎日1回は容器を優しく揺らして、底の氷砂糖を梅全体に行き渡らせるように混ぜます(出来れば2~3回ゆすると良い)。
3.1週間~10日ほどで梅シロップができます。
④アクを取る
1.氷砂糖が溶け切り、梅がシワシワになったら、梅を取り出します。
2.目の細かい清潔な布やキッチンペーパーを敷いたザルなどを使い、シロップをゆっくりとこします。
3.こしたシロップを鍋に入れ、弱火で15分ほど火にかけます。沸騰させないよう注意しながら、表面に浮いてくるアクを取り除きます。
4.鍋ごと冷まし粗熱が取れたら、煮沸消毒した清潔な保存瓶に移し替えて梅シロップの完成です。
梅シロップを作るときのポイント
梅シロップ作りには、あらかじめ梅を冷凍しておくのがおすすめです。冷凍することで梅の細胞が壊れ、通常よりエキスが出やすくなり、シロップが早く完成します。発酵のリスクを減らせる上、旬を過ぎても一年中梅シロップ作りを楽しめるのが大きなメリットです。もし冷凍する時間がない場合は、フォークなどで梅に穴を開けておくと、同様にエキスが出やすくなり、完成までの時間を短縮できますよ。
作っている最中に発酵が進んでしまう場合もあり、白い泡が出て、お酒のような匂いがする場合は発酵している可能性があります。少量であればシロップだけ鍋に移して、弱火にかけながらアクを取り除けば飲めます。異臭がする場合は廃棄しましょう。
保存方法と賞味期限
保存方法は、直射日光のあたらない湿気の少ない冷暗所で保存しましょう。おすすめは冷蔵庫です。
適切に保存すれば、半年〜1年程度は美味しくいただけます。開栓後は、早めに飲みきるのがおすすめです。
5.梅干し・梅シロップ以外の活用法
梅干しには白米で楽しむ方は多いと思いますが、様々な料理に活用できます。また、梅シロップは飲んで楽しむのはもちろん、取り出した梅を再利用しておいしい料理やデザートとしても活用できます。せっかく梅仕事をするなら、他の活用法も知っておくと、梅を余すところなく満喫できますよ!
梅ダレ
梅干しを叩いてペースト状にし、酒、みりん、砂糖、だしなどで調味するだけで簡単に作れます。鶏肉や豚肉のソテーにかけるのはもちろん、冷奴や温野菜にかけても絶品です!
梅味噌
梅と味噌は相性抜群。梅味噌は梅干しを細かく刻み、味噌、砂糖、醤油、みりんなどと混ぜ合わせて作ります。ごはんのお供はもちろん、和え物やドレッシング、魚料理のソースなど、万能調味料として大活躍します。
鮭の梅酢照り焼き
梅干しとお酢を組み合わせて酸味をプラスしさっぱりとした酒の梅酢照り焼きもおすすめです。ポリ袋に鮭と一緒に漬け込むことで、梅の風味がしっかり染み込み、上品な味わいに仕上がります。いつもと一味違う照り焼きが楽しめますよ。
イワシの梅煮
青魚特有の臭みが気になるイワシも、梅と一緒に煮込むことでさっぱりと美味しくいただけます。梅干しの酸味が臭みを和らげてくれるのです。出汁を吸った梅干しもまた一味違う美味しさに変身していますよ。
梅ジャム
梅シロップの梅と砂糖を、レモン汁を煮詰めるだけで、甘酸っぱい絶品ジャムが完成します。パンに塗ったりヨーグルトに入れたり、お菓子作りの材料にしたりと様々な楽しみ方ができます。
梅ゼリー
梅シロップに使った梅の実と、砂糖、水、ゼラチンがあれば作れる手軽なデザートです。材料を火にかけて混ぜ合わせ型に入れて冷やし固めるだけなので、お菓子作りが初めての方でも挑戦しやすいですよ。
6.伊藤農園での柑橘の取り扱い
伊藤農園では、旬の時期には南高梅、そして通年で南高梅を使ったゼリーやサイダー、シロップを販売しております。いずれも添加物不使用で作っておりますので、ぜひ一度お試しください。